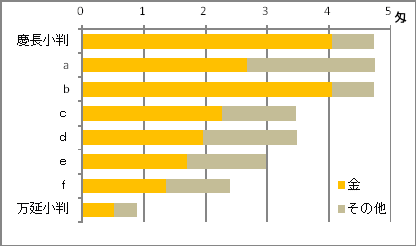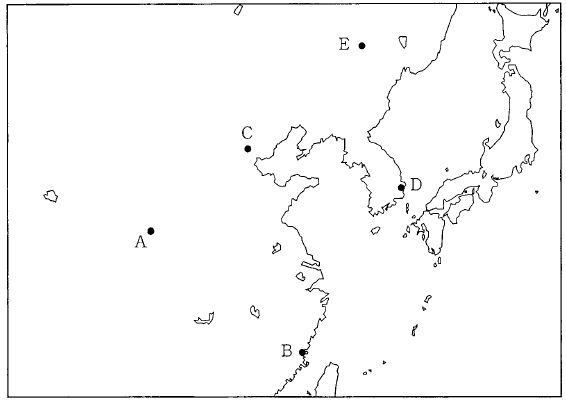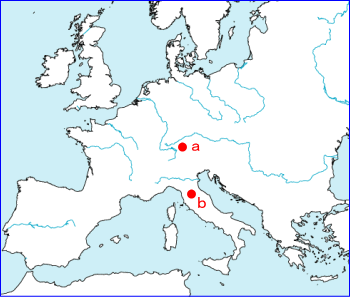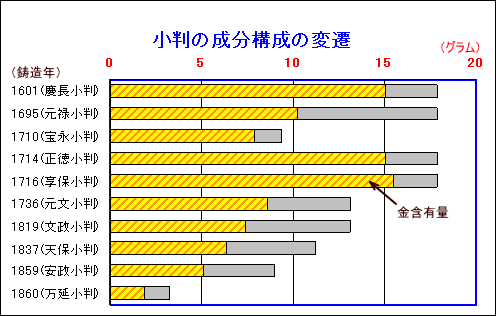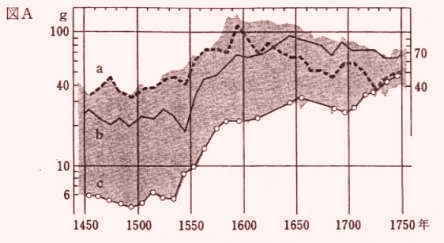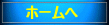足利尊氏が政権の所在地を京都に定めたのは、京都が全国的な経済・商業の中心地であり、そこをおさえることが全国支配のうえから重要と考えたためである。 孫の義満が明に入貢し日明貿易を求めたのは、室町幕府が自ら貨幣を鋳造しなかったので、かわりに(b)明銭を輸入し、国内で流通させるためだった。 日明貿易は1547年の遣明船を最後に断絶した。 16世紀に銀山の開発が進み、日本は世界的な銀産出国となった。 東アジアの貿易は中国の生糸を日本の銀を基軸に展開していった。 倭寇がさかんに活動し、南蛮船が日本に来航した。
近世日本は日明貿易の再開を追及した。 徳川幕府は、豊臣秀吉の唐入り(朝鮮侵略)後、日明講和を交渉した。 それと並行して(c)朱印船を東南アジア各地に渡航させるとともにポルトガル船に糸割符制度を実施し、生糸の一括購入を行った。 また、マニラのスペイン人と交渉し、三浦半島の[ C ]を開港し、メキシコとの貿易を企図した。 しかし日明講和は不調におわり、メキシコ貿易も挫折した。 幕府はヨーロッパ船との貿易を長崎・平戸両港に制限し、島原の乱後、長崎を中国・オランダ船の唯一の貿易港とした。 このほか(d)中国とは朝鮮・琉球を介して日本の銀と中国の生糸が流通した。 17世紀半ば明から清へ王朝が交代したが、日中国交は実現しなかった。
江戸幕府は全国的な統一貨幣として慶長金銀を発行し、続いて[ D ]を鋳造した。 [ D ]は明銭にかわって全国的に流通した。 いわゆる鎖国後も長崎貿易はさかんに行われ、金銀の海外流出が問題になっていった。 新井白石の『折りたく柴の記』によると、金貨の4分の1、銀貨の4分の3が流出したといわれる。 幕府は1685年に中国・オランダ船の貿易高を、それぞれ銀6000貫目、金5万両(銀3000貫目)に制限した。 その後、[ E ]による一定額の貿易を認めた。 1715年に中国船銀6000貫目・オランダ船銀3000貫目の定高は据え置き、そのうちの一定額を[ E ]で支払わせた。 貿易高を制限する一方で、朝鮮人参や生糸の国産化を進め、金銀の流出を抑制した。 (e)白糸の輸入制限を契機に、国内の養蚕業が発展した。
1854年、幕府は日米和親条約を結んで開国し、1858年日米修好通商条約を締結した。 翌年貿易が始まると、金貨が大量に国外に流出したため、幕府は(f)1860年貨幣改鋳を行い対処したが、効果がなかった。 貿易の影響は国内産業におよび、綿糸の輸入増大により綿織物業が、生糸の輸出増大により絹織物業が打撃を受けた。
[問]
1 下線(a)に関連する説明として正しいものはどれか。1つ選びなさい。
ア 平清盛は室津を修築した。
イ 平清盛は保元の乱で崇徳上皇方についた。
ウ 平氏政権は荘園・知行国を経済基盤とした。
エ 平忠盛は日本海の海賊を討ち、平氏台頭の礎を築いた。
オ 平清盛は長崎で宋人を引見した。
2 空欄[ A ]に該当する語句を漢字2字で記入しなさい。
3 空欄[ B ]に該当する語句を漢字5字で記入しなさい。
4 下線(b)に関連する説明として正しいものはどれか。1つ選びなさい。
ア 建長寺船・天龍寺船などによってもたらされた。
イ 洪武通宝
 ・
永楽通宝
・
永楽通宝 ・
天保通宝
・
天保通宝 が全国的に流通した。
が全国的に流通した。ウ 幕府は楽市・楽座令を出し、取引の円滑を図った。
エ 幕府は八幡船の請負商人から抽分銭を取った。
オ 遠隔地間の取引に割符が用いられた。
5 下線(c)に関連する説明として誤っているものはどれか。1つ選びなさい。
ア 1633年に奉書船以外の海外渡航を禁止した。
イ 1631年に奉書船制度に改めた。
ウ 1616年に朱印船の渡航地を拡大した。
エ 1635年に朱印船の海外渡航を禁止した。
オ 1639年に南蛮船の長崎来航を禁止した。
6 空欄[ C ]には幕末外交でも知られた地名が入る。それを漢字2字で記入しなさい。
7 下線(d)に関する説明として誤っているものはどれか。2つ選びなさい。
ア 対馬藩は倭館で朝鮮と貿易を行った。
イ 琉球は中国に朝貢使節を派遣した。
ウ 朝鮮は中国に通信使を派遣した。
エ 琉球は貿易の銀を東南アジアで調達した。
オ 対馬藩は朝鮮人参を日本にもたらした。
8 空欄[ D ]に該当する語句を漢字4字で記入しなさい。
9 空欄[ E ]に該当する語句を記入しなさい。
10 下線(e)に関する説明として正しいものはどれか。1つ選びなさい。
ア 京都の西陣織が消滅した。
イ 足利・桐生で絹織物業がさかえた。
ウ 久留米絣・琉球絣が織られた。
エ 越後縮・薩摩上布が織られた。
オ 尾張・三河で絹織物業がさかえた。
11 下線部(f)のとき鋳造された貨幣として正しいものはどれか。1つ選びなさい。
ア 元文小判 イ 安政小判 ウ 天保小判 エ 文政小判 オ 万延小判
 をクリックすると、参考となるページが表示されます。 もちろん、入試のときはできません。
をクリックすると、参考となるページが表示されます。 もちろん、入試のときはできません。